ワーキングホリデーへの出発を控え、期待に胸を膨らませる一方で、何から手をつけていいか分からない荷造りに、少し不安を感じていませんか。ワーホリの持ち物リストといっても、短期滞在と1年の長期滞在では必要なものが大きく変わります。
ワーキングホリデーの荷物はどれくらいの量で、一体何キロまで許されるのか、スーツケースは何個で、どのくらいの大きさが最適なのか、気になる点は尽きません。特に女子にとっては、美容品や衛生用品など、日本から持っていくべきか悩むアイテムも多いでしょう。また、オーストラリアやカナダといった人気の渡航先ならではの必需品や、経験者が語る本当に持っていってよかったものも知りたいところです。
この記事では、そんなあなたのあらゆる疑問を解消し、安心して準備を進められるよう、印刷も可能な完璧なチェックリストと共に、必要な情報を網羅的に解説していきます。
- ワーキングホリデーに必要な持ち物の全体像がわかる
- スーツケース選びや賢いパッキングのコツが学べる
- 国や滞在期間による持ち物の違いを具体的に理解できる
- 出発前の忘れ物を防ぐための最終チェックリストが手に入る
ワーホリ持ち物リストと荷物の目安

- ワーホリの荷物はどれくらいが目安?
- スーツケースは何個必要?最適な大きさ
- 荷物の重量制限は何キロから注意?
- 効率的に荷物が入るパッキングのコツ
- 海外で役立つおすすめの通信手段とは
ワーホリの荷物はどれくらいが目安?
ワーキングホリデーの荷物の量は、利用する航空会社の規定と、ご自身の渡航スタイルによって大きく左右されます。やみくもに荷物を詰め込む前に、まずは「無料で運べる荷物の量」という物理的な上限を正確に把握することが、賢い荷造りの第一歩となります。
多くの航空会社では、無料で預けられる受託手荷物の個数や重量に上限を設けています。これを超過すると、高額な追加料金が発生してしまうため、注意が必要です。例えば、JALやANAといったフルサービスキャリア(FSC)の場合、エコノミークラスでも23kgまでの荷物を2個まで無料で預けられることが多く、合計46kgという十分な量を運ぶことが可能です。一方で、ジェットスターなどの格安航空会社(LCC)では、受託手荷物は基本的に有料オプションとなっており、予約時に必要な重量分を別途購入する必要があります。
LCC利用時の注意点
LCCは航空券が安いという魅力がありますが、受託手荷物の料金を加算すると、結果的にFSCと変わらない、あるいは高くなるケースも少なくありません。航空券を予約する際は、手荷物料金を含めた総額で比較検討することが非常に重要です。
また、現地でどのような生活を送りたいかによっても荷物の量は変わってきます。都市部で生活し、必要なものは現地で揃えるスタイルであれば荷物は少なくて済みますし、ファームステイなどで頻繁に移動する予定がある場合は、身軽に動けるよう荷物を厳選する必要があります。まずは航空券の規定を確認し、自分の荷物の「上限」を知ることから始めましょう。
スーツケースは何個必要?最適な大きさ

ワーキングホリデーの荷物を運ぶ「器」として、スーツケースの選定は極めて重要です。結論から言うと、最もおすすめの組み合わせは「80L前後の大型スーツケース1個」と「30L以上の機内持ち込み用バックパック1個」です。
航空会社の規定上、スーツケースを2個持っていくことも可能ですが、その代償として移動時の機動性が著しく低下します。空港から滞在先まで公共交通機関を使ったり、エレベーターのないホステルに宿泊したりする場合、一人で2つの大きなスーツケースを運ぶのは想像以上に困難です。このため、主要な荷物は大型スーツケース一つにまとめ、貴重品やPC、数日分の着替えを入れたバックパックを背負うスタイルが、最も現実的で汎用性が高いと言えます。
スーツケースの最適な大きさ
1年間の長期滞在となると、あらゆる季節に対応できる衣類が必要になるため、スーツケースの容量は70Lから90Lの範囲が最もバランスの取れたサイズとされています。これ以上の大きさになると、荷物を満杯に詰めた際に航空会社の重量制限である23kgを超過しやすくなるため、かえって扱いにくくなる可能性があります。
ハードタイプ vs ソフトタイプ
スーツケースの素材には、衝撃に強い「ハードタイプ」と、軽量で柔軟性のある「ソフトタイプ」があります。ワーホリのように荷物が手荒に扱われる可能性や、雨天時の移動を考慮すると、中の荷物を確実に守れるポリカーボネート製の軽量なハードタイプが最もおすすめです。防犯性が高いというメリットもあります。
ワーホリ向けのスーツケース選びについては以下の記事でも詳しく紹介しています。

荷物の重量制限は何キロから注意?

前述の通り、荷物の重量制限は航空会社によって異なりますが、一つの基準として「1個あたり23kg」という数値を覚えておきましょう。これは、多くのフルサービスキャリアがエコノミークラスで設定している無料受託手荷物の上限だからです。
この23kgという重さは、Lサイズのスーツケースに冬物の衣類などを詰め込むと、意外と簡単に到達してしまう重さです。パッキングの際は、こまめにスーツケース全体の重さを測りながら作業を進めることが、空港での超過料金トラブルを避けるための重要なポイントになります。
参考として、主要な航空会社の国際線エコノミークラスにおける手荷物許容量を以下にまとめます。
| 航空会社 | 無料受託手荷物 | 1個あたり重量 | サイズ(3辺合計) |
|---|---|---|---|
| JAL (日本航空) | 2個 | 23kg | 203cm以内 |
| ANA (全日本空輸) | 1~2個* | 23kg | 158cm以内 |
| Jetstar | 0個(有料) | 15kg~40kgで購入 | 規定なし |
*ANAの無料受託手荷物許容量は、購入した運賃規則によって異なります。必ずご自身のeチケットで正確な許容量を確認してください。また、これらの情報は変更される可能性があるため、出発前に必ず利用する航空会社の公式サイトで最新情報を確認することが大切です。
効率的に荷物が入るパッキングのコツ

限られたスーツケースのスペースを最大限に活用するには、いくつかのパッキング技術を知っておくと非常に便利です。ただ詰め込むのではなく、戦略的に荷物を配置することで、より多くのアイテムを、より安全に運ぶことができます。
最も効果的なのが、「トラベルポーチ」と「圧縮袋」の使い分けです。Tシャツや下着、靴下など、種類別に整理したい普段着は、柔軟性のあるトラベルポーチにまとめると、スーツケース内の隙間にフィットさせやすくなります。一方で、ダウンジャケットや厚手のセーターといった、非常にかさばるアイテムは圧縮袋を使って極限まで圧縮するのが賢明です。この使い分けにより、整理のしやすさと省スペースを両立できます。
以下の圧縮袋はトラベルポーチとしても利用できるのでおすすめです。
効果的な重さ配分
スーツケースの安定性を高めるためには、荷物の配置が重要です。靴や書籍、液体類のボトルといった重いものは、スーツケースを立てた時に底になるキャスター側に集中して配置しましょう。これにより重心が下がり、移動時にスーツケースが安定し、転倒しにくくなります。逆に、軽い衣類などは上部に詰めるのが基本です。
機内持ち込みは「サバイバルキット」
機内持ち込み用のバックパックは、単なる手荷物入れではありません。万が一、預けたスーツケースが紛失・遅延する「ロストバゲージ」に備えた、最初の48時間を乗り切るための「サバイバルキット」と位置づけましょう。最低1日分の着替え、洗面用具、常備薬、PCやスマホとその充電器、そして全ての重要書類の原本は、必ず機内に持ち込むようにしてください。
海外で役立つおすすめの通信手段とは

海外に到着してすぐにインターネットに接続できるかどうかは、その後の行動のしやすさを大きく左右します。現代のワーホリにおいて、通信手段の確保は最優先事項の一つです。
現在の主流であり、最もスマートな選択肢が「eSIM」の活用です。eSIMは、物理的なSIMカードを抜き差しすることなく、スマートフォン本体に内蔵されたチップに通信プランをダウンロードして利用する技術です。最大のメリットは、日本にいる間に渡航先のプランを契約・設定しておける点にあります。これにより、現地の空港に到着した瞬間からデータ通信を開始でき、SIMカード販売店を探したり、慣れない言語で契約したりするストレスから解放されます。
渡航初期の1週間〜1ヶ月間はeSIMを利用して、ストレスフリーで生活の立ち上げに集中するのがおすすめです。また、国内キャリアでは楽天モバイルなどの海外ローミングも選択肢に入ります。その後、生活が落ち着いてから、現地の通信会社が提供する、より安価な長期契約の物理SIMカードに切り替えるのが、利便性とコストのバランスが取れた最適な方法と言えるでしょう。
もちろん、Wi-Fiルーターをレンタルする方法もありますが、常に別の機器を持ち歩き、充電する必要があるため、手軽さの面ではeSIMに劣ります。ご自身のスマートフォンの機種がeSIMに対応しているかを確認の上、ぜひ検討してみてください。
どれを利用すればいいか迷っている方は、eSimでは料金とセキュリティ面からSaily、国内キャリアなら安価で手軽に利用できる楽天モバイルのどちらかを利用するのがおすすめです。

ワーホリの持ち物・荷物リストと便利グッズ

- 短期と長期1年で必要な持ち物を比較
- 最適なクレジットカードとデビットカード
- 女子が特に持っていくべきアイテム
- オーストラリア・カナダの持ち物
- 便利グッズや持っていってよかったもの
- ワーホリの持ち物チェックリスト
短期と長期1年で必要な持ち物を比較
ワーキングホリデーの持ち物は、滞在期間によって持参すべき量や種類が大きく異なります。ここでは、3ヶ月程度の「短期滞在」と、1年間の「長期滞在」に分けて、持ち物の考え方の違いを解説します。
短期滞在(1〜3ヶ月)の場合
短期滞在の場合は、必要な消耗品のほとんどを日本から持参することが可能です。特に、シャンプーや化粧品など、肌に直接触れるものは、使い慣れたものを滞在期間分持っていくと安心できます。衣類も、滞在する季節に合わせて1シーズン分を用意すれば十分でしょう。
長期滞在(1年)の場合
一方で、1年間の長期滞在となると、全ての消耗品を日本から持っていくのは現実的ではありません。基本戦略は、「日本製品でないと困るもの」を厳選し、それ以外は「現地調達」を前提とすることです。例えば、シャンプーやボディソープは最初の数日分だけトラベルサイズで持参し、その後は現地のスーパーで購入します。衣類も、渡航時の季節のものを中心に持っていき、季節が変わるタイミングで現地で購入したり、古着屋を活用したりするのが賢明です。特に、かさばる冬用のコートなどは、渡航先で購入する方が荷物を大幅に減らせます。
期間に関わらず日本から持参すべきもの
滞在期間の長短にかかわらず、以下のアイテムは日本からの持参を強くおすすめします。
- 常備薬:飲み慣れた日本の薬が一番安心です。
- 高品質な下着・靴下:海外製品は品質やサイズが合わないことが多いです。
- 基礎化粧品(特に化粧水):海外では日本の「化粧水」のようなアイテムは一般的ではありません。
- 切れ味の良い爪切りや耳かき:日本製品の品質は非常に高いです。
最適なクレジットカードとデビットカード

海外での生活において、現金を大量に持ち歩くのは非常に危険です。安全かつスマートな資金管理のためには、複数の金融ツールを戦略的に組み合わせることが不可欠です。
まず、メインの決済手段となるのがクレジットカードです。世界中のほとんどの場所で利用できるVisaかMastercardのブランドを、最低でも2枚持っていくことを強く推奨します。これにより、片方のカードが紛失や磁気不良で使えなくなっても、もう片方で対応できるというリスク分散になります。
「海外事務手数料」に注意
海外で日本のクレジットカードを利用すると、利用額に対して1.6%〜3.85%程度の「海外事務手数料」が上乗せされます。この手数料はカード会社によって異なるため、年会費やポイント還元率だけでなく、この手数料が低いカードを選ぶことが、年間を通じた大きな節約につながります。
ワーホリの救世主「Wiseデビットカード」
近年、ワーホリ生活者の資金管理に革命をもたらしているのが、Wise(ワイズ)のデビットカードです。これは、アプリ内で日本円を実際の為替レートで40種類以上の通貨に両替し、チャージしておける画期的なカードです。現地での支払いはもちろん、ATMから現地通貨を非常に低い手数料で引き出せるため、ワーホリに行くなら絶対に持っていくべき一枚と言えます。
日常の支払いが必要な場面では「クレジットカード」か「Wiseデビットカード」を使い、現地通貨が必要になった時に「Wiseデビットカード」でATMから引き出す、という使い分けです。この組み合わせで、リスクを分散しつつコストを最小化できます。
Wiseの特徴や使い方については以下でも詳しく紹介しています。

女子が特に持っていくべきアイテム

ワーキングホリデーの準備において、女性ならではの視点でこだわりたい持ち物があります。些細なことのように思えても、日々の快適さを大きく左右する重要なアイテムです。
最も多くの経験者が挙げるのが、日本製の基礎化粧品です。特に、海外では一般的なスキンケアの習慣が異なり、日本の「化粧水」にあたる製品がほとんど見つかりません。また、ファンデーションなどのベースメイクも、色味や質感が日本のものとは大きく異なるため、肌が敏感な方やこだわりのある方は、最低でも数ヶ月分は持参することをおすすめします。また、生理用品なども海外での購入は可能ですが、品質や使用感は日本製品が優れているとの声が多いです。
下着やストッキングも日本から!
海外で販売されている下着は、デザインは豊富でも、日本人女性の体型に合わないサイズ感であったり、生地が良くなかったりすることが少なくありません。また、海外の強力な洗濯機で傷みやすいため、品質の良い日本製のものを少し多めに持っていくと、長期にわたって快適に過ごせます。ストッキングやタイツ類も同様に、品質と価格の面で日本からの持参が賢明です。
オーストラリア・カナダの持ち物

ワーキングホリデーの持ち物は、渡航先の気候や文化に合わせて最適化することで、より快適で安全な生活を送ることができます。ここでは、人気の2カ国に特化した持ち物戦略を紹介します。
オーストラリア:太陽と自然の国
南半球に位置するオーストラリアで最も重要なのは「徹底した紫外線対策」です。日本の3〜5倍とも言われる強力な紫外線から身を守るため、以下の3点は必需品とも言えます。
- SPF値の高い、使い慣れた日本の日焼け止め
- 顔の形にフィットしやすい日本のサングラス
- 広いつばの帽子
また、コンセントの形状が「Oタイプ」のため、変換プラグは必ず複数個用意しましょう。
カナダ:雄大な自然と厳しい冬
カナダでの生活、特に冬を越す予定がある場合に最も重要なのは「本格的な防寒着は現地で調達する」という戦略です。日本の冬物ではカナダの極寒に対応できない可能性が高く、現地の気候に合わせて設計されたダウンコートやスノーブーツを現地で購入するのが最も合理的です。日本からは、ユニクロのヒートテックのような高機能インナーを複数枚持っていくと、重ね着(レイヤリング)に非常に役立ちます。また、冬は非常に空気が乾燥するため、保湿力の高いスキンケア用品も必須です。
イギリスに行くなら「硬水対策」も
もし渡航先がイギリスの場合、忘れてはならないのが「硬水対策」です。イギリスの水道水はミネラル分を多く含む硬水で、日本のシャンプーが泡立ちにくく、髪がゴワゴワになる原因となります。現地で硬水用のシャンプーを購入するか、日本から硬水に対応したシャンプーを持参すると、髪のストレスを大幅に軽減できます。
便利グッズや持っていってよかったもの

ワーキングホリデーの準備では、パスポートや衣類といった基本的な持ち物リストを揃えることが最優先です。しかし、実際に海外で生活を始めると、「これを持ってきて本当に良かった」と心から思える、生活の質(QOL)を劇的に向上させてくれるアイテムがいくつか存在します。ここでは、多くの経験者が挙げる、リストには載りにくいながらも非常に役立つ便利グッズと、逆に「不要だった」と判断されがちなアイテムについて、その理由と共に詳しく解説していきます。
モバイルバッテリー
現代の海外生活において、スマートフォンは単なる連絡手段ではなく、地図、翻訳機、財布、情報収集ツールといった役割を担う生命線です。外出先でバッテリーが切れてしまうと、道に迷ったり、友人と連絡が取れなくなったりと、深刻な事態に陥りかねません。そのため、最低でもスマートフォンを2〜3回フル充電できる大容量のモバイルバッテリーは、もはや必需品と言えるでしょう。
特にワーホリ中は、慣れない土地でGoogleマップを頻繁に利用したり、写真を撮ったりと、スマートフォンのバッテリー消費が激しくなります。また、ホステルや古いアパートではコンセントの数が限られていたり、ベッドから遠い位置にあったりすることも珍しくありません。モバイルバッテリーがあれば、コンセントの場所を気にせず、自分のベッドでくつろぎながら充電することも可能です。
以下のAnkerのバッテリーはコンパクトかつ大容量のため普段使いにもおすすめです。
コンセント不足を解消する電源タップ
モバイルバッテリーと並んで、充電に関する悩みを解決してくれるのがコンパクトな電源タップです。海外の宿泊施設では、部屋にあるコンセントが一つか二つだけ、というケースが非常に多くあります。スマートフォン、ノートPC、カメラ、モバイルバッテリーなど、充電したい電子機器は意外と多いもの。そんな時、電源タップが一つあるだけで、状況は一変します。
一つのコンセントを3〜4口に増設できるため、変換プラグも一つで済み、自分の全てのデバイスを同時に充電できるようになります。友人との旅行中にコンセントをシェアしたり、カフェで電源を借りる際に「少しだけ貸して」とお願いしやすくなったりと、人間関係をスムーズにする効果も期待できるかもしれません。USBポートが複数付いているタイプを選ぶと、ACアダプターが不要なケーブルを直接挿せるため、さらに荷物をコンパクトにできておすすめです。
以下の記事では海外対応の電源タップについて詳しくまとめています。

VPN(Virtual Private Network)
VPNは、デジタル時代のワーキングホリデーにおける「見えないお守り」です。これは、インターネット上の通信を暗号化し、安全な接続を確保するためのサービスで、主に「セキュリティ強化」と「日本のオンラインサービス利用」という二つの大きなメリットがあります。
セキュリティ強化
カフェや空港、ホステルなどのフリーWi-Fiは非常に便利ですが、セキュリティが脆弱で、通信内容を第三者に盗み見られる(ハッキングされる)危険性も否定できません。VPNを利用すれば、通信が暗号化されるため、クレジットカード情報やパスワードといった個人情報を安全に保護しながらインターネットを利用できます。
日本のサービス利用
海外からのアクセスを制限している日本の動画配信サービス(TVer、U-NEXT、Huluなど)は、通常の状態では視聴できません。しかし、VPNを使って日本のサーバーに接続することで、あたかも日本国内からアクセスしているかのように見せかけることができ、海外にいながら日本のテレビ番組やドラマを楽しむことが可能になります。
銀行のオンラインバンキングにアクセスする際のセキュリティ対策から、日本のエンタメで息抜きをする時間まで、VPNはワーホリ生活のあらゆる場面でサポートしてくれます。
特にNordVPNはセキュリティ面でも信頼性が高く、キャンペーンも随時行われているためおすすめです。

逆に「不要だったもの」は?
一方で、善意で持ってきたものの、結果的に「日本に置いてくればよかった…」と後悔につながりやすいアイテムもあります。荷物を減らし、より快適な旅にするために、これらのアイテムについても知っておくことも役立ちます。
1. 多すぎる衣類
特に、日本のトレンドに合わせたおしゃれ着や、たくさんのアクセサリーは出番がほとんどないことが多いです。ワーキングホリデー中のライフスタイルは、多くの国で日本よりカジュアルであり、結局は着心地が良くて洗いやすいお気に入りの数着を繰り返し着ることになります。多くの国ではファストファッションブランドが安価で手に入り、季節の変わり目に買い足すことも容易です。
2. 基本的な日本食
醤油や味噌、みりんといった基本的な調味料やインスタント食品は、重くてかさばる上に、主要都市であればアジアングロッサリーストアで比較的手軽に入手可能です。もちろん日本で購入するより割高にはなりますが、スーツケースの貴重なスペースと重量を消費してまで運ぶメリットは小さいと言えるでしょう。ただし、地方のファームなどに行く場合は事情が異なるため、ご自身の滞在先に合わせて判断する必要があります。
3. ほとんどの場合で不要な「変圧器」
「海外=変圧器が必要」というイメージは過去のものとなりつつあります。近年製造されているスマートフォンやノートPC、デジタルカメラなどの充電器は、そのほとんどが「100-240V」のグローバル対応製品です。製品のACアダプターに記載されている「INPUT(入力)」の項目を確認し、「100-240V」と書かれていれば変圧器は不要で、渡航先のコンセント形状に合わせる「変換プラグ」さえあれば世界中で使用できます。無駄な重りになる可能性が非常に高いので、持っていく前に必ず手持ちの電化製品を確認しましょう。
ワーホリの持ち物チェックリスト
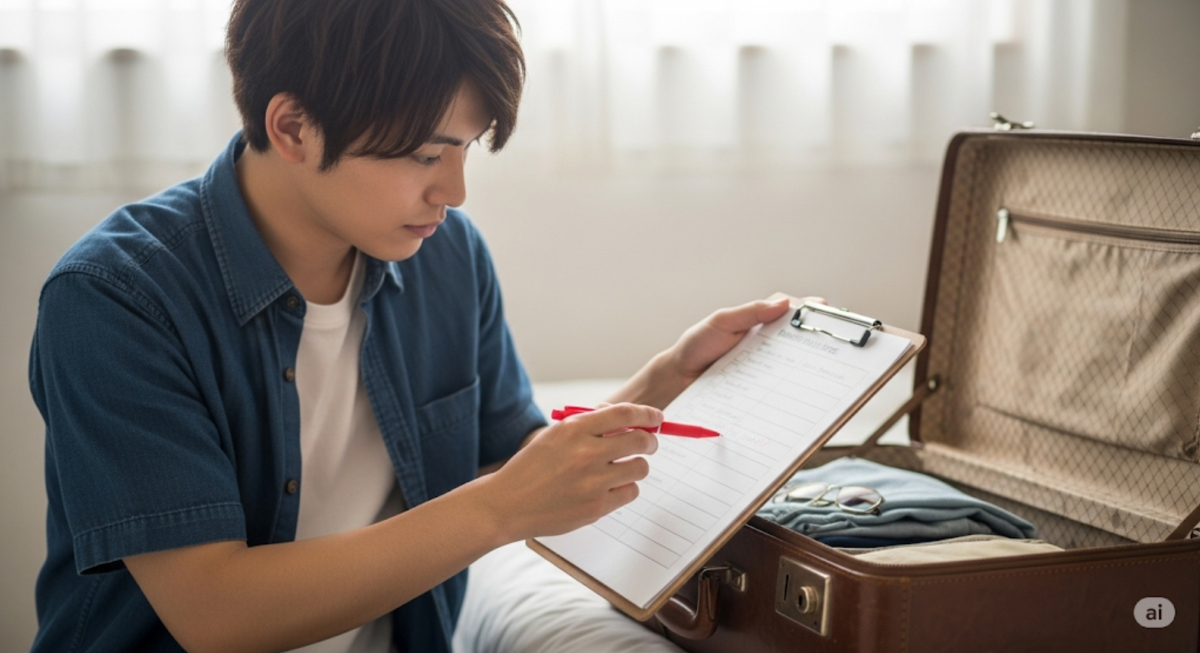
いよいよ出発が近づいたら、最後の忘れ物チェックです。ここでは、これまで解説してきた内容を網羅した、印刷して使える便利な持ち物チェックリストを用意しました。スーツケースに入れたもの、機内持ち込みバッグに入れたものを、一つずつ確認しながら準備を完成させましょう。ご自身の渡航先やスタイルに合わせて、項目の追加や削除をしてご活用ください。
ワーキングホリデー持ち物チェックリスト
| カテゴリー | アイテム名 | 推奨/備考 | |
| 重要書類・手続き関連 | パスポート(原本) | 滞在期間をカバーする有効期限が十分にあるか必ず確認。顔写真ページのコピーとデータも準備。 | □ |
| ビザ発給許可証 | スマートフォンでの画面提示だけでなく、必ず印刷して持参。 | □ | |
| 航空券(eチケット控え) | 入国審査で提示を求められることがあるため、印刷しておくと安心。 | □ | |
| 海外旅行保険証書 | 滞在期間全てをカバーしているか確認。保険会社の連絡先も控えておく。 | □ | |
| 英文残高証明書 | 国によっては入国時に提示を求められる。発行から1ヶ月以内のものが望ましい。 | □ | |
| 国際運転免許証 | 現地で運転する予定がある場合のみ。日本の免許証も一緒に携帯する必要がある。 | □ | |
| 語学学校の入学許可証 | 該当する場合のみ。 | □ | |
| お金・金融関連 | 現地通貨(現金) | 2〜3万円程度。空港から滞在先までの交通費や、到着直後の軽食代など、カードが使えない場面に備える。 | □ |
| 日本円(現金) | 1万円程度。帰国時の交通費などのために持っておくと安心。 | □ | |
| クレジットカード | Visa/Mastercardを最低2枚。海外事務手数料が低いカードがおすすめ。 | □ | |
| Wiseデビットカード | 為替レートが良く、現地ATMからの現金引き出しに非常に便利。 | □ | |
| 電子機器関連 | SIMフリースマートフォン | 日本でSIMロックを解除しておく。 | □ |
| ノートPC / タブレット | 仕事探しや情報収集に。 | □ | |
| モバイルバッテリー | 外出時の必需品。リチウムイオン電池のため、必ず機内持ち込み手荷物に入れる。 | □ | |
| 各種充電ケーブル | 断線や紛失に備え、予備を1本ずつ持っていくと安心。 | □ | |
| 電源変換プラグ | 渡航先のコンセント形状に合ったものを複数個用意。全世界対応タイプも便利。 | □ | |
| イヤホン | 長距離フライトやシェアハウスでの騒音対策に。ノイズキャンセリング機能付きがおすすめ。 | □ | |
| 衣類・ファッション小物 | Tシャツ・カットソー(5〜7枚) | 着回しの効くベーシックなデザインが中心。 | □ |
| 長袖シャツ・ブラウス(2〜3枚) | 面接にも使えるきれいめのものを1枚入れておくと良い。 | □ | |
| ズボン・ジーンズ(2〜3本) | □ | ||
| パーカー・カーディガン | 体温調節用に。 | □ | |
| 防水・防風ジャケット | 天候の変化に対応できるアウター。 | □ | |
| 軽量ダウンジャケット | コンパクトに収納できるものが便利。かさばる本格的な冬用コートは現地調達がおすすめ。 | □ | |
| 下着・靴下(10〜14日分) | 日本製の品質が良く、サイズも合うため多めに持参することを強く推奨。 | □ | |
| パジャマ・部屋着(2セット) | □ | ||
| フォーマルな服(1セット) | 面接や少し良いレストランに行く際に。 | □ | |
| スニーカー、サンダル | 履き慣れたものを。 | □ | |
| サングラス、帽子 | 特にオーストラリアなど日差しが強い国では必須。 | □ | |
| 洗面用具・化粧品 | 歯ブラシ・歯磨き粉 | 海外の歯ブラシはヘッドが大きいものが多いため、日本のものがおすすめ。歯磨き粉は最初の数日分でOK。 | □ |
| スキンケア用品(化粧水など) | 化粧水は海外では入手しにくいため、肌に合うものを日本から持参することを強く推奨。 | □ | |
| メイク用品 | 特にファンデーションなど、色味が重要になるベースメイクは日本から持参が安心。 | □ | |
| 日焼け止め | 使い慣れた日本のものがおすすめ。 | □ | |
| 生理用品 | 品質や使用感が日本製品と大きく異なるため、こだわりがある方は日本から持参。 | □ | |
| 爪切り・耳かき・綿棒 | 日本製品の品質が高いため、持参がおすすめ。 | □ | |
| コンタクトレンズ・洗浄液 | 現地での購入は手続きが煩雑な場合があるため、滞在期間分を持参するのが最も確実。 | □ | |
| 医薬品 | 常備薬 | 鎮痛剤、風邪薬、胃腸薬、かゆみ止めなど、必ず使い慣れた日本の薬を持参。 | □ |
| 処方薬 | 滞在期間分を用意し、英文の処方箋(薬剤証明書)も携帯する。 | □ | |
| 絆創膏・消毒液 | □ | ||
| 日用品・雑貨 | 洗濯ネット(4〜5枚) | 海外の洗濯機は水流が強力なため、衣類を守るために必須。 | □ |
| 速乾性のタオル(2〜3枚) | □ | ||
| 折りたたみ傘(晴雨兼用) | □ | ||
| S字フック | クローゼットがない部屋などで収納スペースを確保できる便利グッズ。 | □ | |
| 日本のお土産 | 抹茶味のお菓子や高品質な文房具など、かさばらないものが喜ばれる。 | □ |
ワーホリの持ち物リストと荷物について総括
ワーキングホリデーの準備は、単なる荷造りではなく、これから始まる1年間の生活を設計する創造的なプロセスです。この記事で紹介したポイントを参考に、あなただけの完璧な持ち物リストを完成させてください。最後に、充実したワーホリ生活を送るための持ち物準備の要点をまとめます。
- パスポートとビザの有効期限は出発前に必ず再確認する
- 海外旅行保険は滞在期間の全てをカバーするものに加入する
- 航空会社の無料受託手荷物の重量と個数の上限を把握する
- スーツケースは80L前後の大型1個とバックパックの組み合わせが最適
- パッキングキューブと圧縮袋を戦略的に使い分ける
- 重い荷物はスーツケースの下側(キャスター側)に詰める
- 機内持ち込み手荷物は万が一に備えたサバイバルキットと心得る
- 現金は最小限にし、クレジットカードとWiseデビットカードを併用する
- 渡航初期はeSIMを利用し、その後現地の長期SIMに切り替えるのが賢明
- 基礎化粧品や生理用品など、肌に触れるものは日本からの持参が安心
- 下着や靴下など、品質にこだわりたい衣類も日本から持っていく
- 本格的な防寒着は渡航先の気候に合わせて現地で購入する
- 渡航先のコンセント形状に合わせた変換プラグを複数個用意する
- 日本の包丁や浄水器など、生活の質を上げる便利グッズも検討する
- 出発直前には必ずチェックリストを使って最終確認を行う





