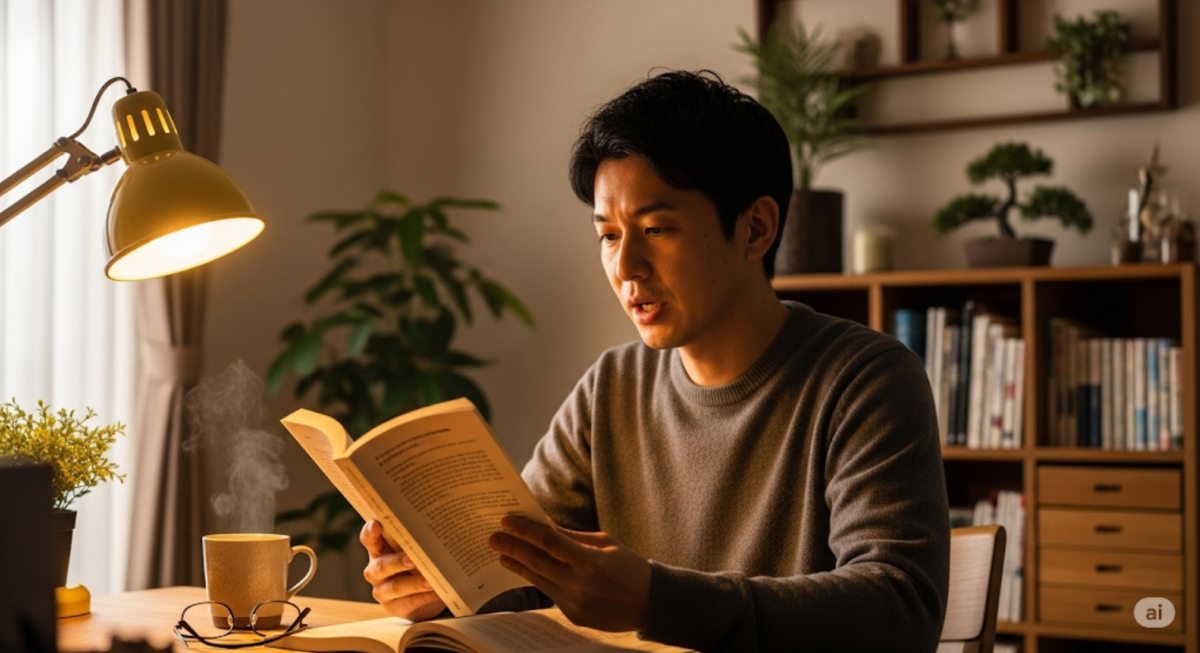「英語の長文になると、途端に内容が頭に入ってこない」「単語はわかるのに読めない理由が知りたい」と悩んでいませんか。中学生や高校生の頃から英語を勉強してきたのに、社会人や大人になった今でも長文読解にストレスやイライラを感じる方は少なくありません。
それは、あなたが英語が読めない病気だからではなく、これまで行ってきた学習方法そのものに原因があるのかもしれません。この問題の根本的な原因を理解し、正しいやり方と学習方法に切り替えることで、英語力は飛躍的に向上します。鍵となるのは、日本語を介さず英語を直接理解する英語脳の構築です。
この記事では、従来の暗記型学習から脱却し、リスニングや楽しいストーリー、物語を活用しながら、あなたに合った教材で無理なく英語脳を育てるアプローチを解説します。
- 英語の長文が読めない根本的な原因
- 単語が分かっても読めない脳の仕組み
- 日本語に訳さず読む「英語脳」の作り方
- レベル別・目的別のおすすめ学習法と教材
英語の長文が読めない根本的な原因とは
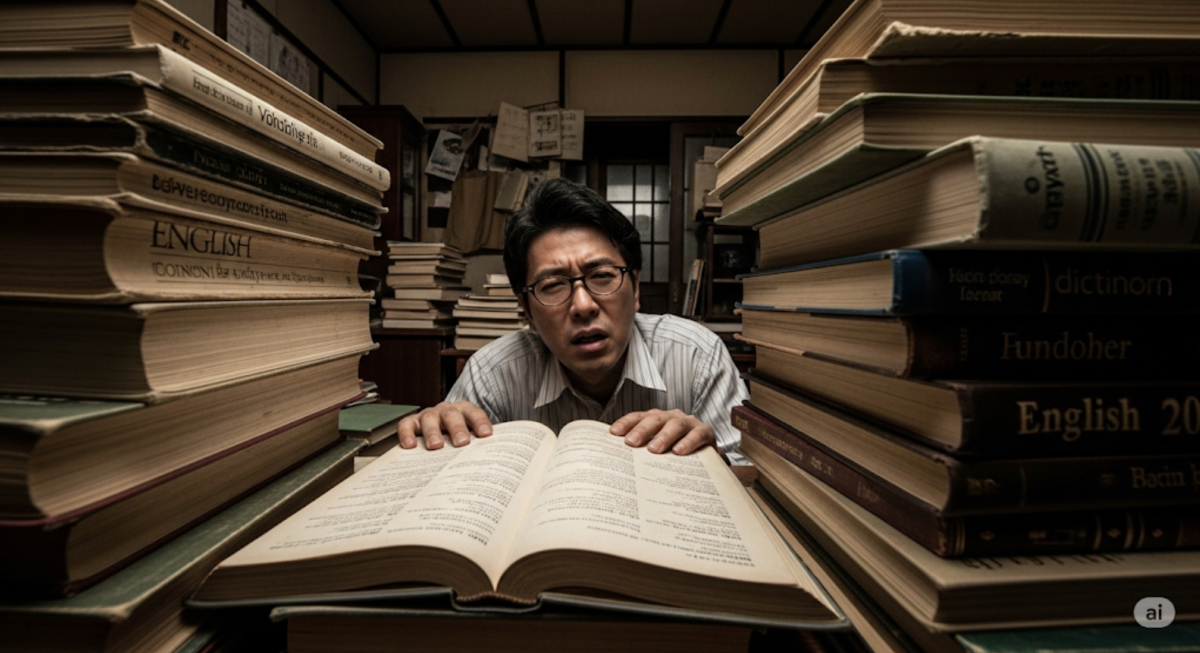
- 英語の長文が読めない原因とは
- 単語はわかるのに読めない理由
- 内容が頭に入ってこないのはなぜ?
- 英語が読めないのは病気なのか
- 中・高校生と社会人や大人の違い
英語の長文が読めない原因とは
多くの日本人学習者が英語の長文読解に苦戦する最大の原因は、学校で長年慣れ親しんできた「文法訳読方式」という勉強法にあります。
これは、英文を文法的に細かく分解し、単語を一つひとつ日本語に訳しながら意味を理解しようとするアプローチです。この方法は、テストで高得点を取るための分析的な読解には役立つ側面もありますが、流暢に英語を読む能力の育成を妨げる大きな要因となります。
文法訳読方式が引き起こす主な問題点は以下の通りです。
返り読みの習慣化
日本語と英語は語順が根本的に異なります(日本語:SOV型、英語:SVO型)。このため、英文を日本語の語順に当てはめて理解しようとすると、必然的に文の末尾から前方へ視線を戻す「返り読み」が発生します。この習慣が定着すると、英文を読むスピードが著しく低下し、リアルタイムでの内容理解が困難になります。
思考の翻訳癖
常に日本語を介して英語を理解しようとすると、「英語を英語のまま捉える」という思考回路が育ちません。ネイティブスピーカーが話す自然なスピードの会話や、長文の内容をスムーズに処理するためには、この「翻訳癖」から脱却する必要があります。
大学入試が与える影響
日本の英語教育は、大学入試の内容に大きく影響されます。難解な長文や細かい文法知識を問う試験が多いため、学校の授業も「試験対策」に偏りがちになります。これによりコミュニケーション能力よりも分析的なスキルが優先され、結果として流暢な読解力を身につける機会が失われてしまうのです。
このように、あなたが長文を読めないと感じるのは、能力や努力が不足しているからではなく、これまで受けてきた教育が「速く読む」ことよりも「正確に訳す」ことに重点を置いていたためだと言えます。
単語はわかるのに読めない理由
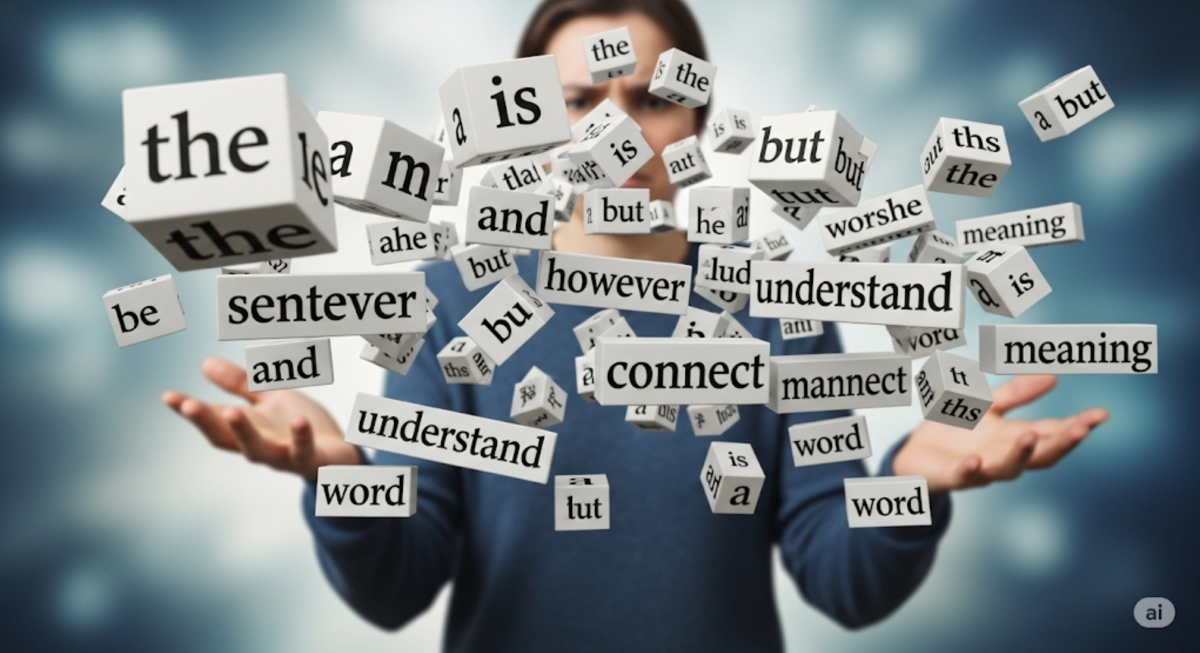
「一つひとつの単語の意味はわかるのに、文章全体として何を言っているのか理解できない」という経験は、多くの学習者が抱える共通の悩みです。この現象は、人間の脳の情報処理能力の限界、特に「ワーキングメモリ」と「認知的負荷」という観点から科学的に説明できます。
読解やリスニングには、大きく分けて2つのプロセスが存在します。
- 知覚プロセス:文字や音声を個々の単語として認識する処理。
- 理解プロセス:認識した単語を文法に沿って統合し、意味のあるメッセージとして構築する処理。
理想的な状態は、①の知覚プロセスが「自動化」され、脳のリソースをほとんど消費せずに行われることです。これにより、脳は②の理解プロセスに十分なリソースを割くことができます。
しかし、多くの日本人学習者の場合、この知覚プロセスが自動化されていません。不慣れな英単語や文の構造を認識するだけで、脳の作業台である「ワーキングメモリ」が一杯になってしまうのです。
その結果、文の後半を読んでいる頃には、前半の内容を記憶しておくための脳の容量が足りなくなり、情報が抜け落ちてしまいます。これが、「単語は点としてわかるが、文という線として繋がらない」という現象の正体です。
認知的負荷理論(Cognitive Load Theory)
この理論では、学習中の精神的負荷を3種類に分類します。
- 内因的負荷:課題そのものの難しさ
- 外因的負荷:不適切な学習法による不要な負荷
- 本質的負荷:実際の学習(知識の構築)に向けられる良い負荷
従来の翻訳中心の学習は、この「外因的負荷」を極端に高めてしまいます。効果的な学習とは、この不要な負荷を減らし、脳のリソースを本質的な学習に向けることです。
つまり、単語はわかるのに読めないのは、一つひとつの単語を認識する作業に脳がエネルギーを使いすぎて、文章全体の意味を理解するための余力がなくなっている状態だと言えます。
内容が頭に入ってこないのはなぜ?
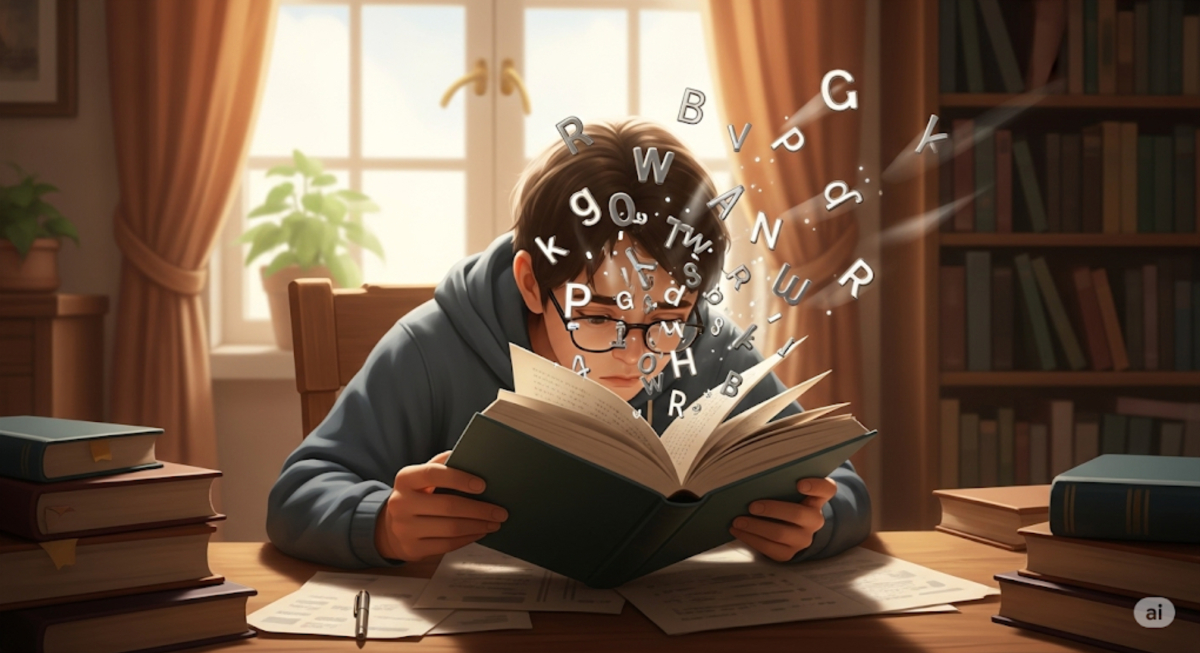
英語の内容がすんなり頭に入ってこない感覚は、前述のワーキングメモリの問題に加え、日本語と英語の「言語的距離」が大きく影響しています。これは単に単語が違うというレベルではなく、言語の根幹をなすシステムが脳の情報処理に与える影響です。
語順の壁:SVOとSOV
最も大きな違いは語順です。英語は「主語(S)→動詞(V)→目的語(O)」の順で文が構成されます。例えば「I eat sushi.」のように、誰が何をするのかという重要な情報が文の序盤で提示されます。
一方、日本語は「主語(S)→目的語(O)→動詞(V)」が基本です。「私は寿司を食べる。」のように、文の結論となる動詞が最後にきます。このため、日本語を母語とする私たちの脳は、文の最後まで聞かないと全体の意味が確定しない「動詞待ち」の処理に慣れています。
この日本語的な処理モードのまま英語を読むと、脳は本来すぐに処理すべき動詞の情報を保留し、文末まで待とうとしてしまいます。このタイムラグと脳内での語順の並べ替え作業がメモリに多大な負荷をかけ、「内容が頭に入ってこない」という感覚の直接的な原因となるのです。
音とリズムの壁
リスニングだけでなく、読解時の「内なる音読(黙読)」においても、音とリズムの違いは処理の妨げになります。
- 音素の違い:英語には/r/と/l/、/th/など日本語にない音が多く、これらを脳内で正確に再現できないと、単語の認識が遅れます。
- リズムの違い:日本語がすべての音をほぼ均等な長さで発音するのに対し、英語は重要な単語(内容語)を強く、文法的な単語(機能語)を弱く発音する「強勢拍リズム」です。このリズム感に慣れていないと、どこで意味が区切れるのか直感的に把握しにくくなります。
これらの「語順の壁」と「音とリズムの壁」が同時に脳を襲うことで、情報処理が上手くできないケースが起こります。これが、個々の単語は拾えても、文全体の意味を構築する前に情報が抜け落ちてしまう脳の仕組みだと言えます。
英語と日本語の言語的な違いについては以下の記事でも紹介しています。
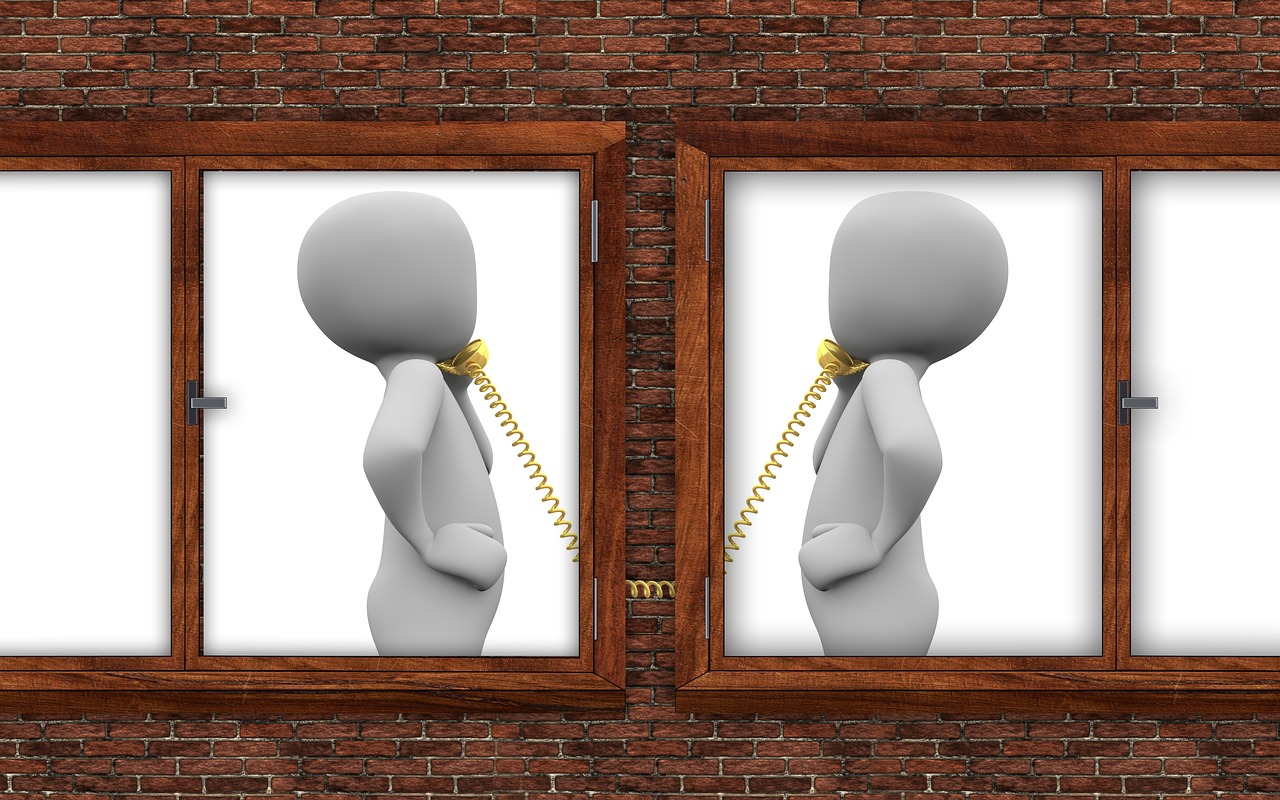
長文が読めないのは病気なのか
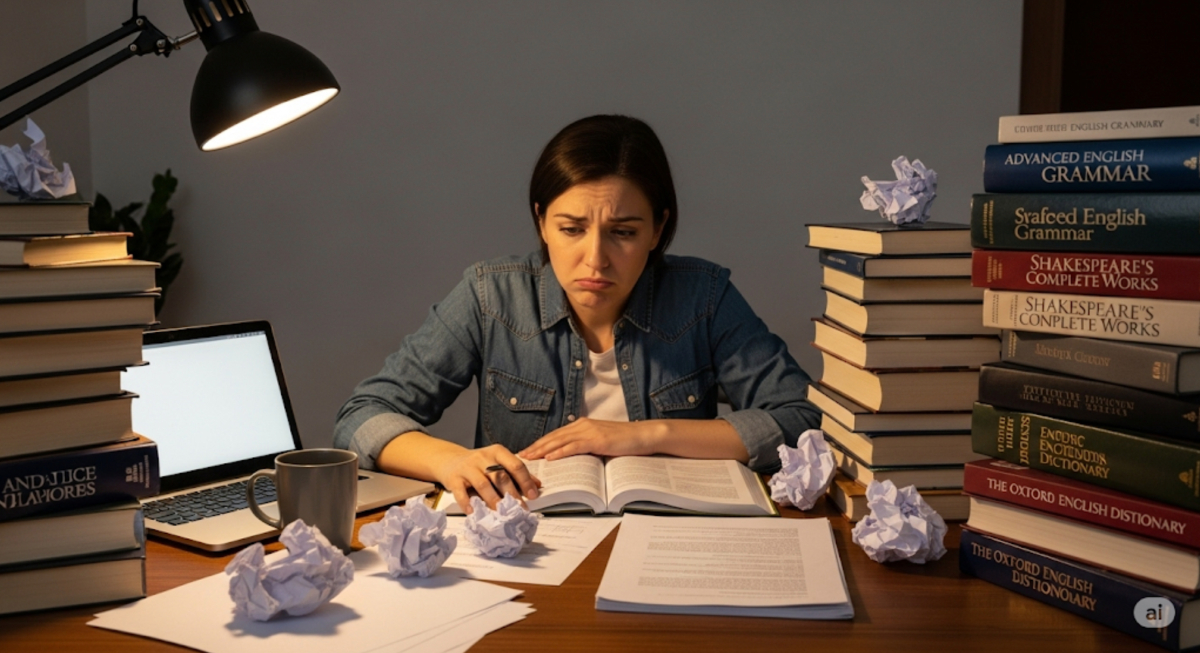
長年にわたり英語学習を続けているにもかかわらず、一向に長文が読めるようにならない状況に、「自分は英語が読めない病気なのではないか」と深刻に悩んでしまう方もいるかもしれません。
しかし、これは決して特殊な才能や能力の問題ではありません。むしろ、これまでの学習方法が意図せずして作り出してしまった「学習性障害」に近い状態と考えることができます。
「学習性障害」というと少し大げさに聞こえるかもしれませんが、これは「流暢に読むスキル」とは逆行するスキル(細かく分解して日本語に訳すスキル)を熱心に訓練し続けた結果、脳がその非効率な処理方法に最適化されてしまった状態を指します。
この「英語が読めない病気」の正体は、以下の悪循環によって形成されています。
- 非効率な処理:翻訳や返り読みが癖になり、読むのが遅く、脳に高い負荷がかかる。
- 練習不足:負荷の高い作業は苦痛で長続きしないため、英語に触れる絶対量が不足する。
- 自動化の欠如:大量のインプットがないため、単語認識などの処理がいつまでも自動化されない。
- ①に戻る…
このサイクルに一度はまってしまうと、同じ方法で「もっと頑張る」だけでは、壁を乗り越えることは非常に困難です。努力すればするほど、非効率な処理方法が強化されてしまう可能性すらあります。
唯一の対策は「学習法の転換」
この悪循環を断ち切る唯一の対策は、学習の前提を根本から変えることです。具体的には、脳にかかる認知的負荷を劇的に下げ、苦痛なく大量の英語に触れられる環境を作ること。それこそが、この「病」を克服するための最も効果的な処方箋となります。
重要なのは、「自分には才能がない」と諦めるのではなく、「やり方が間違っていただけだ」と認識することです。正しいアプローチに切り替えれば、誰でも自然に読めるようになります。
中・高校生と社会人・大人の違い

英語の長文読解でつまずく原因は、学習を始めた年代や目的によっても少し異なります。ここでは、中学生・高校生と社会人・大人が直面しがちな壁の違いと、それぞれが意識すべきポイントを解説します。
中学生・高校生が直面する壁
学生にとって最大の壁は、前述の通り「受験」です。定期テストや大学入試では、文法知識の正確さや複雑な構文を分析する能力が問われることが多いため、授業も自然と「試験のための英語」になりがちです。
- デメリット:流暢さよりも正確さが重視されるため、間違いを恐れる気持ちが強くなる。速読や多読といった、量をこなすトレーニングの機会が少ない。
- 対策:学校の勉強とは別に、自分のレベルに合った簡単な読み物を趣味として取り入れることが非常に効果的です。試験勉強の息抜きにもなり、将来的に役立つ「使える英語力」の土台を築けます。
社会人・大人が直面する壁
一方、社会人や大人の学習者が直面するのは、学生時代とは異なる種類の壁です。
- デメリット:学生時代に身につけた「文法訳読方式」から抜け出せない。仕事や家庭が忙しく、まとまった学習時間を確保するのが難しい。すぐに成果が出ないとモチベーションが低下しやすい。
- 対策:「学習」という意識を捨て、「楽しむ」ことに焦点を当てるのが成功の鍵です。通勤時間や家事の合間に英語のポッドキャストを聞いたり、寝る前に好きなジャンルの洋書を少し読んだりと、ライフスタイルの中に英語を溶け込ませる工夫が求められます。完璧を目指さず、継続することを最優先しましょう。
年代別の課題と対策
| 年代 | 主な壁(原因) | 効果的な対策 |
|---|---|---|
| 中学生・高校生 | 受験英語による「返り読み」や「分析癖」の定着 | 試験勉強とは別に、趣味として簡単な物語などを多読する |
| 社会人・大人 | 過去の学習法の固執、時間不足、モチベーション維持の難しさ | 「勉強」ではなく「娯楽」と捉え、スキマ時間を活用して英語に触れる習慣を作る |
どちらの年代にも共通して、従来の「勉強」という概念から一度離れてみることが、長文を読む上でのブレークスルーに繋がるはずです。
英語の長文が読めない人向けの学習方法

- 日本語に訳さない英語脳の構築
- 英語脳におすすめの多読と多聴
- ストーリーや物語でのインプット
- リスニングと並行して学ぶ必要性
- ストレスなく続けられる教材選び
日本語に訳さない英語脳の構築
英語の長文が読めないという根本的な問題を解決する鍵は、「英語脳」を構築することにあります。英語脳とは、決して非現実的な概念ではありません。簡単に言えば、「日本語を介さずに、英語を英語の語順のまま自動的に処理する神経回路」のことです。
私たちが日本語の文章を読むとき、いちいち他の言語に翻訳したり、文法を分析したりはしません。言葉を見て、あるいは聞いて、瞬時にイメージや意味を理解しています。この状態を英語でも実現するのが、英語脳のゴールです。
ここで大切になるのが、言語学者スティーブン・クラッシェンが提唱した「習得」と「学習」の違いです。(参考:クラッシェンが唱えた第二言語習得5つの仮説)
- 学習 (Learning):文法規則を意識的に勉強し、知識として覚えること。日本の学校教育の中心です。
- 習得 (Acquisition):子どもが母語を身につけるように、大量のインプットを通じて無意識的に言語能力を獲得すること。
クラッシェンは、流暢な言語運用能力は「学習」からではなく、この「習得」から生まれると主張しました。英語脳は、文法の部品を意識的に組み立てて作るのではなく、適切な栄養(=大量の理解可能なインプット)が与えられたときに、自然に成長していきます。
つまり、長文読解の問題を解決するには、これまでの「学習」中心のアプローチから、「習得」中心のアプローチへとパラダイムシフトする必要があります。目標は「英語について知っている」状態から、「英語が(無意識に)使える」状態へと移行することです。
この英語脳を構築することで、返り読みや翻訳癖といった非効率な癖から解放され、ネイティブスピーカーに近いスピードと感覚で長文を読めるようになります。
英語脳については、以下でも詳しく解説しています。

英語脳におすすめの多読と多聴

英語脳を育てるための最も効果的で科学的根拠のある学習方法が、「多読(Extensive Reading)」と「多聴(Extensive Listening)」です。
これは、難しい文章を精読するのではなく、自分のレベルにとって「易しい」と感じる素材を、大量に読み・聞くというアプローチです。この方法の目的は、知識を増やすことではなく、英語を英語のまま処理する脳の回路を鍛え、自動化することにあります。
多読・多聴を実践する上で重要なのが、以下の「多読三原則」です。
多読三原則
- 辞書は引かない:文脈から意味を推測する訓練をします。流れを止めないことが最優先です。
- わからないところは飛ばす:完璧な理解にこだわらず、楽しさとリズムを維持します。
- つまらなくなったらやめる:モチベーションが最も重要です。楽しめない素材は習得の妨げになります。
これらの原則は、学習に伴うストレス(情意フィルター)を下げ、インプットの量を最大化するために設計されています。

「i-1」から始める重要性
言語習得理論では、自分のレベルより少し上の「i+1」のインプットが重要だとされます。しかし、翻訳癖を矯正し、流暢な処理能力を身につける初期段階では、あえて自分のレベルより「易しい」と感じる「i-1」の素材を選ぶことが重要です。
自分にとって易しい素材を読むことで、脳は初めて「翻訳せずに、立ち止まらずに、流暢に」英語を処理する成功体験を積むことができます。この高速処理スキルが土台として確立されて初めて、「i+1」のインプットから真に恩恵を受けられるようになるのです。
具体的なやり方としては、まず自分のレベルに合った簡単なストーリーや絵本から始め、毎日少しずつでも読み進めていくことです。「勉強」ではなく「読書」として楽しむことが、英語脳を育てる最短の道となります。
初心者向けの学習するポイントについては以下でも紹介しています。

ストーリーや物語でのインプット

多読・多聴を実践する上で、「ストーリー」や「物語」が効果的です。その理由は、単に面白いからというだけではありません。物語は、人間の脳が最も効率的に情報を処理し、記憶できるように最適化された形式だからです。
脳は物語を記憶するようにできている
人間の脳は、事実の羅列よりも、登場人物、設定、展開といった文脈を持つ物語の形で提示された情報をはるかに記憶しやすいようにできています。脳科学の研究では、物語を読むと、言語処理に関わる領域だけでなく、内容に応じて感覚や運動に関わる領域まで活性化することが分かっています。これにより、より豊かで全体的な脳の体験が生まれ、記憶に定着しやすくなるのです。
ナラティブ・トランスポーテーション理論
ナラティブ・トランスポーテーション理論は、読者が物語の世界に「没入する」心理状態を説明する理論です。魅力的な物語に引き込まれると、私たちは「ゾーン」と呼ばれる状態に入りやすくなります。この状態では、文法を分析したり、頭の中で翻訳したりといった意識的な思考が減り、「次に何が起こるのか」に完全に集中できます。これこそが、言語を無意識的に習得するための理想的な状態だと言えます。
物語が言語習得を加速させる仕組み
- 自然な文脈の提供:単語や文法が、意味のある文脈の中で提示されるため、意味の推測が容易になり、記憶にも残りやすくなります。
- 感情移入による記憶強化:登場人物への共感が、記憶を強くします。感情を揺さぶられた出来事は、そうでないものより鮮明に記憶に残ります。
- 自然な形での反復練習:重要な単語や構文が、物語の中で自然な形で何度も繰り返し登場します。これにより、退屈なドリル学習なしで、習得に必要な反復が確保されます。
結論として、物語は単なる教材の一つではなく、言語習得に必要な要素(理解可能な内容、文脈、感情移入)をすべて詰め込んだ、究極のインプット学習だと言えます。勉強での苦痛を減らし、楽しさを最大化するために、ぜひストーリーの力を活用してください。
リスニングと並行して学ぶ必要性

英語脳の構築において、多読(リーディング)と多聴(リスニング)は、別々に行うよりも並行して実践することで、学習効果を飛躍的に高めることができます。これらは互いに補完し合い、相乗効果を生み出します。
リーディングがリスニングを支える仕組み
リーディングは、語彙と文法の知識を蓄える主要な供給源です。そもそも知らない単語や文の構造は、聞いても認識することができません。多読を通じて脳内に膨大な単語と文型パターンのライブラリを構築することで、それらが音声として現れたときの認識速度が格段に向上します。
また、リーディングは次にどのような言葉が来るかを予測する力を養います。これは、一瞬で消えていく音声を処理するリスニングにおいても重要なスキルとなります。
リスニングがリーディングを支える仕組み
一方、リスニングは文字情報と音声情報を結びつける役割を果たします。英語の自然なリズム、強勢、イントネーションを脳に刷り込むことで、単語単位ではなく、意味のあるかたまり(チャンク)で文章を処理する能力が向上し、英語を読む能力も向上します。
学習法の例:RWL (Reading While Listening)
テキストを読みながら、その音声ナレーションを同時に聞く「RWL」は、効果的な学習テクニックの一つです。この方法には以下のようなメリットがあります。
- 認知的負荷の軽減:音声が発音を補ってくれるため、脳は意味理解に完全に集中できます。
- 記憶への定着:単語の「見た目」と「音」が強固に結びつき、語彙の習得率が最も高まることが研究で示されています。
- 返り読みの矯正:音声のペースに合わせて読み進めることで、物理的に返り読みができなくなり、前から順番に理解する癖がつきます。
このように、リーディングとリスニングは、一方が「何を言うか(語彙・文法)」を、もう一方が「どう言うか(発音・リズム)」を教え合うループを形成します。どちらか一方だけを練習するよりも、最初から両者を学習する方が、効率的に全体の英語力を引き上げることができるはずです。
ストレスなく続けられる教材選び

多読・多聴を成功させ、英語脳を育てる上で最も重要な決断の一つが「教材の選び方」です。教材の選択そのものが、学習成果に影響すると言っても過言ではありません。ここでは、ストレスなく学習を継続するための教材選びとおすすめを紹介します。
重要ポイント:「簡単」と感じるレベルから始める
前述の通り、特に学習の初期段階では、自分の実力よりも明らかに「易しい」と感じるレベル(i-1)の教材を選ぶことが成功の鍵です。具体的には、1ページに知らない単語が1〜2個程度、あるいは全くないレベルが理想です。
プライドが邪魔をして難しいものに挑戦したくなるかもしれませんが、目的は知識を増やすことではなく、「翻訳せずにスラスラ読める」という脳の回路を鍛えることです。この成功体験が自信と楽しさを生み、学習を継続させる原動力となります。
レベル別のおすすめ教材
初心者(TOEIC〜550点目安):
- Storyline Online:子供向けの絵本を朗読してくれるサイトで、イラストが内容理解をサポートしてくれます。YouTubeの字幕機能でスクリプトを確認することもできます。
- Storynory:短編の物語・ストーリーを無料で学習することができます。文章と音声の両方で利用することができます。
- グレーデッド・リーダーズ (Graded Readers):使用される語彙が学習者向けに合わせられた書籍シリーズです。できるだけ易しいレベルから始めましょう。
中級者(TOEIC 550〜785点目安):
- ヤングアダルト (YA) 小説:『ハリー・ポッター』シリーズなど、若者向けに書かれた小説はストーリーが面白く、大人向けの文学よりも平易な言葉で書かれています。
- 学習者向けポッドキャスト:BBC 6 Minute EnglishやVoice of Americaなど、スクリプト付きの明瞭な発音で話してくれるサイトがおすすめです。
中・上級者(TOEIC 785点以上):
- 一般向け小説・ノンフィクション:自分の興味がある分野のベストセラー小説や、Kindle Unlimited、Audibleなどのサービスを活用して多読・多聴を進めます。
- ネイティブ向けポッドキャスト:TED Talksやニュース、趣味に関する番組など、興味の幅を広げていきましょう。
教材選びで避けるべき点は、「無理な背伸び」です。難しい教材を選んでしまうと、結局は昔の文法訳読方式に逆戻りしてしまい、ストレスを感じて挫折する原因となります。常に「楽しいか」「楽に読めるか」を自問自答しながら、教材を選ぶようにしましょう。
以下でも無料で英語学習に利用できる教材を多く紹介しています。

総括:英語の長文が読めない原因と対策
この記事では、英語の長文が読めない原因から、その問題を根本的に解決するための「英語脳」の作り方までを解説しました。最後に、重要なポイントをリストで振り返ります。
- 英語の長文が読めない最大の原因は文法訳読方式にある
- 返り読みや翻訳癖は読解スピードを著しく低下させる
- 単語がわかっても読めないのは脳のワーキングメモリが限界だから
- 解決策は日本語を介さず英語を直接理解する英語脳の構築
- 英語脳は意識的な学習ではなく無意識的な習得によって育つ
- おすすめの学習方法はレベルに合わせた多読と多聴
- 辞書は引かずわからないところは飛ばすのが多読の原則
- 教材は簡単すぎると感じるレベルから始めるのが成功の鍵
- 物語やストーリーは脳が最も効率的に言語を習得できる形式
- リーディングとリスニングの並行実践は学習効果を最大化する
- 音声付きの教材でRWLを実践するのが非常に効果的
- 中学生や高校生は受験勉強とは別に趣味として多読を取り入れる
- 社会人や大人は勉強と気負わず楽しむことを最優先する
- 大切なのは才能ではなく正しいやり方で継続すること
- これらのアプローチで英語が読めない悩みから卒業しよう