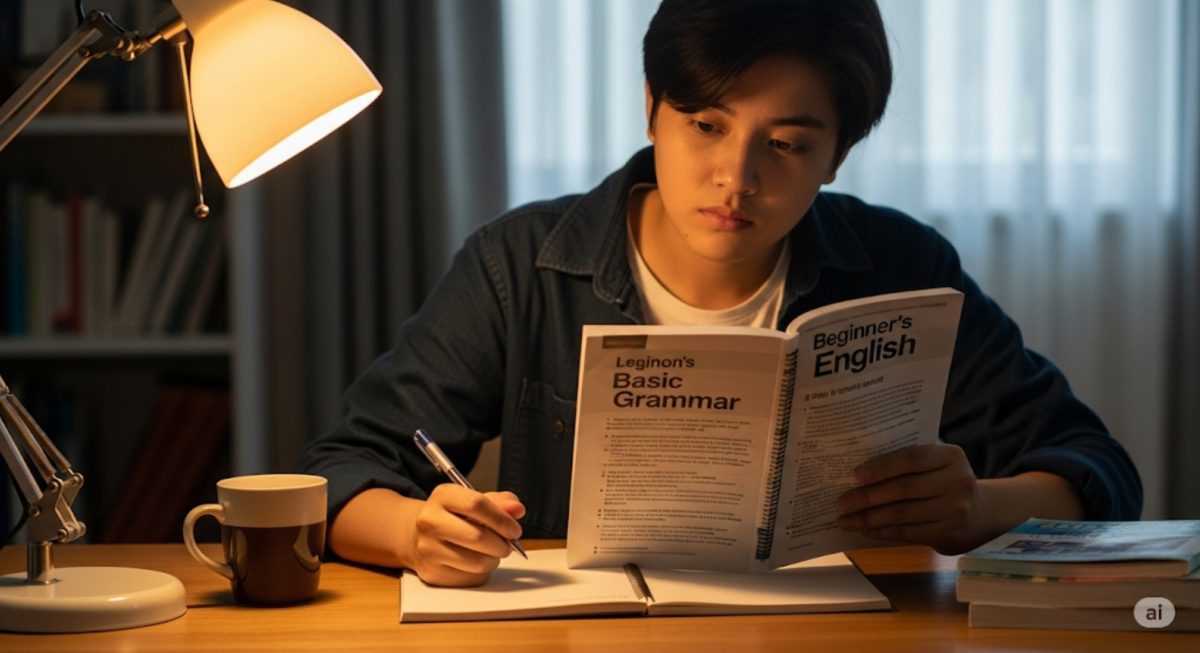「英語の基礎固めをしたいけど、一体何から始めたらいいんだろう…」「中学生や高校生の時に勉強したはずなのに、全然話せない」と感じていませんか。
実は、多くの英語が苦手な日本人が同じ悩みを抱えています。基礎から勉強したいという意欲はあっても、正しいやり方が分からず、効果のない学習を続けているケースが少なくありません。その根本的な原因は、英語を日本語に訳して理解しようとする従来の学習方法にあります。
この記事では、英語を英語のまま直接理解する「英語脳」の育て方に焦点を当てます。英語脳を鍛えることで、リスニング力が向上し、学習効率が飛躍的に高まります。まず1ヶ月で実践できる具体的なステップから、忙しい社会人でも継続できる学習法、教材やアプリの選び方、そして多くの人が気になる「ペラペラになるまで何年かかるのか」という疑問まで、あなたの英語学習に関するあらゆる問いに答えていきます。今度こそ、挫折しない英語の基礎固めを始めましょう。
- 従来の英語学習法がなぜ非効率なのかが分かる
- 挫折しないための鍵となる「英語脳」の概念を理解できる
- 英語脳を育てるための具体的な学習ステップが分かる
- 自分に合った教材やアプリを見つけ、学習を継続できる
英語の基礎固めを始める際の考え方
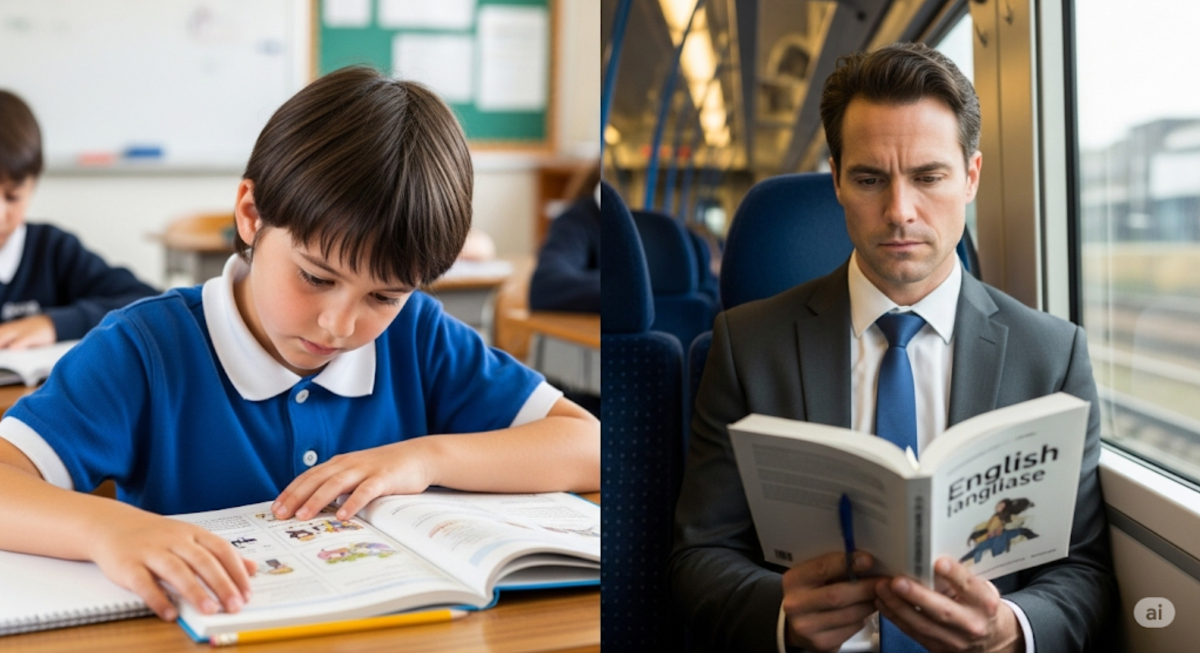
- 英語が苦手な日本人が陥る勉強法の罠
- 英語脳を意識した学習のメリット
- 基礎から勉強したい人が知るべきこと
- 英語脳を育てるためのアプローチ
- ペラペラになるまで何年かかる?
英語が苦手な日本人が陥る勉強法の罠
多くの日本人が英語学習でつまずく大きな原因は、中学・高校で徹底的に教え込まれた「文法訳読方式」にあります。これは、英文を日本語の語順に直し、文法ルールを分析しながら正確に翻訳する学習法です。
この方法でテストの点数は取れるようになるかもしれませんが、リアルタイムのコミュニケーション能力を育てる上では、むしろ足かせとなってしまいます。なぜなら、英文を読むたびに後ろから訳し返す「返り読み」や、話す前に頭の中で日本語の文章を組み立ててから英語に変換する「翻訳癖」が染み付いてしまうからです。
ネイティブスピーカーの会話スピードは1分間に150語以上にもなります。このような速いスピードの中で、いちいち翻訳していては到底追いつけません。これが、時間をかければ文章は読めるのに、リスニングやスピーキングが全くできないという「英語が苦手な日本人」を量産してきた大きな原因なのです。
「翻訳癖」がもたらすデメリット
- 会話の反応が著しく遅れる
- 思考が追いつかず、途中でフリーズしてしまう
- 脳に大きな負担がかかり、すぐに疲れてしまう
- 日本語の直訳になり、不自然な英語(ジャパングリッシュ)になる
「試験では高得点が取れたのに、簡単な会話すらできない…」という経験はありませんか?それはあなたの能力の問題ではなく、学習方法そのものに原因があったのかもしれません。
英語脳を意識した学習のメリット

では、翻訳癖から抜け出すにはどうすればよいのでしょうか。その答えが「英語脳」を育てることにあります。英語脳とは、日本語を介さずに、英語を英語のまま直接的に思考・理解する脳の働きのことです。
例えば、”apple”と聞いたり見たりしたときに、「りんご」という日本語を思い浮かべるのではなく、赤くて丸い果物のイメージが直接頭に浮かぶ状態を指します。この思考回路が構築されると、英語学習の効率は劇的に向上します。
翻訳という余計なプロセスがなくなるため、脳の認知的負荷が大幅に軽減され、より速く、より多くの英語を処理できるようになるのです。これにより、長時間の学習やコミュニケーションも苦にならなくなり、学習効率そのものが飛躍的にアップします。
英語脳がもたらす3つの主なメリット
1. 処理速度の向上
リスニングやリーディングの速度がネイティブのスピードに近づき、会話のレスポンスも速くなります。
2. 認知的負荷の軽減
翻訳作業による精神的な疲労がなくなるため、長時間の学習や実践が可能になります。
3. 自然な表現力の獲得
日本語を介さないことで、ネイティブが使う自然な言い回しやコロケーションが直接身につきます。
つまり、英語の基礎固めとは、単語や文法を覚えること以上に、この「英語脳」という土台をいかに構築するかが重要になると言えるでしょう。英語脳については以下の記事でも解説しています。

基礎から勉強したい人が知るべきこと

これから英語の基礎を本気で固めたいと考えているなら、まず言語がどのように習得されるのか、その科学的なメカニズムを理解することが近道です。言語学者スティーブン・クラッシェン博士は、言語能力の発達には2つの異なるプロセスがあると提唱しました。
- 習得 (Acquisition):子どもが母語を身につけるように、無意識的・直感的に言語を内面化するプロセス。流暢に「使える」能力はここから生まれます。
- 学習 (Learning):学校の授業のように、文法ルールなどを意識的に勉強するプロセス。言語「についての知識」は得られますが、流暢な会話能力には直結しません。
この理論が示す重要な結論は、言語を流暢に使えるようになるための王道は、意識的な「学習」ではなく、無意識的な「習得」にあるということです。そして、習得を引き起こす唯一の方法が、「理解可能なインプット(Comprehensible Input)」に大量に触れることだとされています。
理解可能なインプットとは?
自分の現在のレベル(i)より、ほんの少しだけ難しいレベル(+1)のインプット(リスニングやリーディング)のことです。簡単すぎず、難しすぎて意味が全く分からないわけでもない、少し挑戦的な内容に触れ続けることで、脳は自然に次のレベルへと移行していきます。
つまり、分厚い文法書を解読したり、単語リストを丸暗記したりするのではなく、自分が楽しめる、かつ少しだけ挑戦的なレベルの英語の物語を聞いたり読んだりすることに時間を費やしましょう。
英語脳を育てるためのアプローチ

英語脳を効率的に育てるには、「大量のインプット」を主軸に、「アウトプット」と「インタラクション(対話)」を組み合わせたサイクルを回していくのが効果的です。これは、それぞれが独立しているのではなく、相互に作用し合う一つのシステムのようなものだとも言るでしょう。
英語脳を育てる学習サイクル
1. インプット(燃料)
まず、大量の理解可能なインプット(多読・多聴)を脳に取り込み、言語のパターンや語彙に関するデータベースを無意識下に構築します。これが全ての土台となる燃料です。
2. アウトプット(診断)
次に、インプットした知識を使って実際に話したり書いたりしてみます。この試みによって、自分が何を理解していて、何がまだ使えないのか、知識の「穴」が明確になります。アウトプットは、自身の能力を診断するツールとして機能します。
3. インタラクション(調整・洗練)
そして、他者との対話の中でアウトプットを試みます。コミュニケーションがうまくいかない時、相手が別の言葉で言い換えたり、こちらが質問したりする過程で、自分に最適なレベルのインプットが提供され、知識の「穴」が埋まっていきます。
このサイクルが回転することで徐々に理解が増し、学習がどんどん加速していきます。まずはインプットに8割以上の時間を割き、アウトプットやインタラクションは残りの時間で行うくらいのバランスから始めるのがおすすめです。
英語脳を作るためのアプローチや学習方法を詳しく知りたい方は、以下で紹介している書籍も参考になります。

ペラペラになるまで何年かかる?

「この学習法で、どれくらいの期間でペラペラになりますか?」これは誰もが抱く疑問ですが、結論から言うと、「ペラペラ」の定義と学習強度に大きく依存します。
一般的に「業務で支障なく使えるレベル」を指すCEFR B2レベルに到達するには、500〜600時間の学習が必要とされています。しかし、これは英語と言語的距離が近いヨーロッパ言語話者の場合です。日本語話者の場合、その数倍の時間がかかると考えるのが現実的です。
米国の政府機関FSI(外交官養成局)のデータによると、英語話者が日本語を習得するには約2,200時間かかるとされています。これを参考に、日本人学習者向けの現実的なタイムラインの目安を以下に示します。
| レベル(CEFR) | 能力記述の目安 | 推定累積学習時間 | 1日1時間の学習 | 1日3時間の学習 |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 身近な話題について要点を理解し、基本的な対応ができる | 約800時間 | 約2.2年 | 約9ヶ月 |
| B2 | ネイティブと緊張せず自然にやり取りができる(業務レベル) | 約1,200時間 | 約3.3年 | 約1.1年 |
| C1 | 複雑な文章を理解し、流暢かつ自然に自己表現ができる | 約2,200時間 | 約6年 | 約2年 |
この表が示すように、流暢さの獲得は数ヶ月で達成できるものではなく、数年単位のコミットメントを要する長期的なプロジェクトです。「すぐにペラペラになる」という幻想は捨て、焦らず着実に学習を継続することが、成功への唯一の道だと言えるでしょう。

英語の基礎固めと英語脳を育てるやり方

- 英語の基礎を学ぶ具体的なステップ
- 初心者や1ヶ月目は何から始める?
- 多読・多聴のメリットと学習のコツ
- シャドーイングのメリットとやり方
- 中学生・高校生と社会人のポイント
- 自分に合った教材・アプリの選び方
英語の基礎を学ぶ具体的なステップ
ここからは、英語脳を効率的に育て、英語の基礎を固めるための具体的なステップを3段階に分けて詳しく解説します。初心者の方でも迷わず取り組めるよう、各段階での目標と具体的な学習方法をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
ステップ1:思考の土台作り(学習開始〜数ヶ月)
最初の1ヶ月は、英語学習において最も重要な期間と言っても過言ではありません。この段階の目標は、単語や文法を覚えることではなく、日本語を介さず英語で直接考える「思考の土台」を築くことです。
まず、お手持ちの英和辞書や日本語訳付きの教材は一旦脇に置きましょう。代わりに、写真やイラストが豊富なモノリンガル(英語のみ)の絵辞典や、Googleの画像検索を活用します。例えば、「desk」と調べて、たくさんの机の画像を見ながら「desk」と発音することで、「desk = 机」という翻訳を経由せず、「desk ⇔(机のイメージ)」という直接的な結びつきを脳内に作っていきます。
この土台作りで効果的なのが、「環境描写(Environmental Narration)」というトレーニングです。これは、自分の身の回りにあるものや、自分自身の行動を、知っている限りの簡単な英語でつぶやく練習法になります。「This is a pen. I am writing. I feel happy.」のように、文法が間違っていても、単語の羅列になっても全く問題ありません。完璧を目指さず、頭に浮かんだことをそのまま英語で口に出す癖をつけることが、このステップの大切なポイントです。
これら訓練を続けることで、英語を見るとすぐに日本語に訳そうとする「翻訳癖」が弱まり、その後の学習効率も向上するはずです。
ステップ2:理解力の構築(インプット中心)
思考の土台ができてきたら、次は大量の「理解可能なインプット」を通じて、語彙や文法のパターンを無意識に吸収していく段階に入ります。ここでの主役は、多読・多聴(Extensive Reading/Listening)です。
多読・多聴の基本的な原則は、「辞書なしで95%以上理解できる、簡単で楽しめる素材を、大量に、速く読む・聞く」ことです。難しいニュース記事や専門書に挑戦する必要はありません。むしろ、少し簡単すぎると感じるくらいのレベルが最適です。
利用する学習教材の例は以下のようになります。
- 学習者向けのYouTubeチャンネルやポッドキャスト:ゆっくり、はっきりとした英語で話してくれるものが多く、リスニングの入り口として最適です。
- レベルに合った簡単な書籍やストーリー:学習者向けの書籍や子ども向けの絵本などもおすすめです。簡単なレベルから始め、1冊読み終える達成感を味わいましょう。
ステップ3:運用能力の活性化(アウトプット練習)
大量のインプットによって英語のデータベースが脳内に蓄積されてきたら、いよいよその知識を実際に「使う」練習を取り入れていきます。この段階の目標は、インプットした知識をアウトプットを通じて活性化させ、より洗練された運用能力へと高めることです。
ただし、いきなりネイティブと会話するのはハードルが高いと感じるかもしれません。そこで、プレッシャーの少ない状況で始められるアウトプット練習が有効です。
- シャドーイング(Shadowing):ネイティブの音声を聞きながら、少し遅れて影(シャドー)のように真似て発音する練習法です。これはリスニング力と発音を同時に鍛えられる、非常に効果的なトレーニングとなります。
- 英語での日記(English Journaling):自分の考えや一日の出来事を英語で書く練習です。これは「スローモーションでのスピーキング」とも言え、時間をかけて語彙を選んだり文章を構成したりする良い訓練になります。
初心者や1ヶ月目は何から始める?

これまでの話を踏まえると、英語の基礎固めの第一歩として取り組むべきことは明確です。それは、「翻訳回路を強制的に遮断し、英語とイメージを直接結びつける練習」から始めることです。
多くの学習者は、新しい単語に出会うとすぐに「日本語の意味は何か?」と考えてしまいます。しかし、この思考こそが英語脳の構築を妨げる最大の壁です。まずはこの習慣を断ち切る必要があります。
具体的な方法としては、日本語が一切書かれていない、できれば音声付きの教材を使うのが理想的です。例えば、写真やイラストが豊富な「ピクチャーディクショナリー(絵辞典)」を活用し、絵を見て、対応する英単語を発音するという練習を繰り返します。これにより、脳内に「りんごの絵 ⇔ appleという単語」という直接的なリンクが形成されていきます。
この段階では、たくさんの単語を覚えようと焦る必要はありません。目的は、日本語を介さずに世界を認識する新しい思考回路の「土台」を築くことです。この土台がしっかりしていれば、その後の学習の伸びが全く違ってきますよ。
まずは身の回りにあるものからで構いません。机、椅子、ペン、ドアなど、目に見えるものと英単語を直接結びつけるトレーニングから始めてみましょう。
以下でも初心者が始める上でのポイントについて紹介しています。

多読・多聴のメリットと学習のコツ
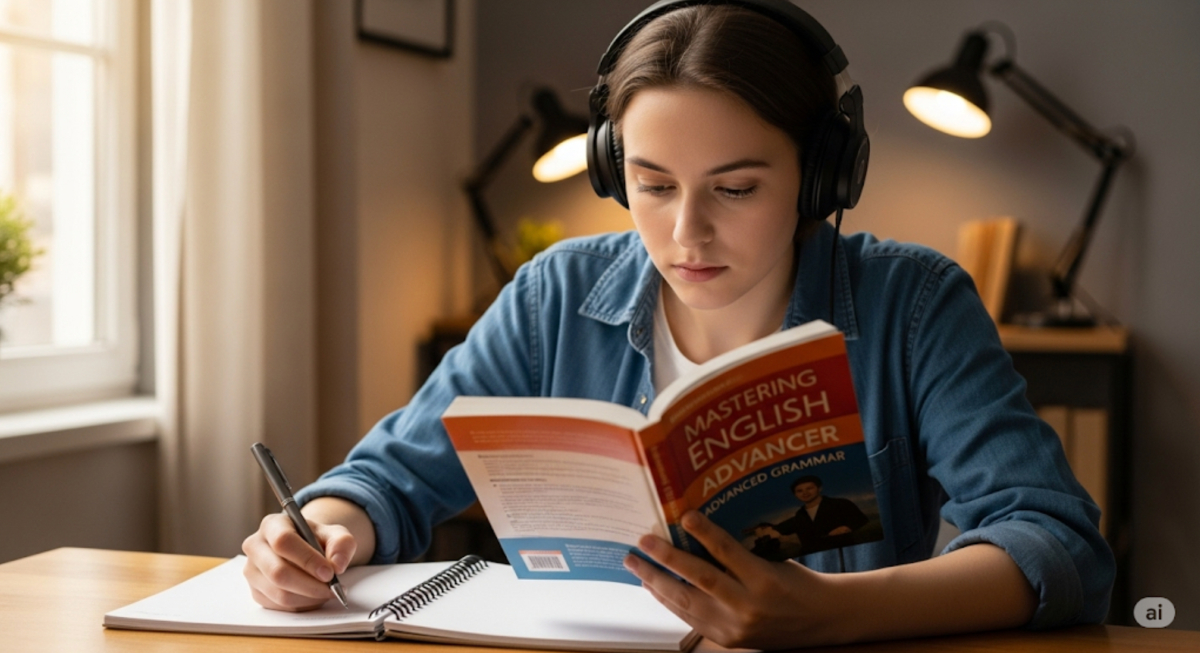
英語脳を育てるためのインプット学習において、その中核を担うのが「多読・多聴」です。これは、簡単な英語を「たくさん」「速く」読んだり聞いたりする学習法を指します。一見、ただ本を読んだり音声を聞いたりするだけのシンプルな行為ですが、これこそが英語力を飛躍させる最も強力なエンジンとなります。ここでは、多読・多聴がもたらす絶大な効果と、失敗せずに実践するための具体的なやり方のポイントを解説します。
なぜ効果がある?脳が自然に学ぶメカニズム
多読・多聴がなぜこれほどまでに効果的なのか、その背景には脳が言語を自然に習得するメカニズムが関係しています。主な効果は以下の3つです。
1. 語彙が「使える知識」として定着する
単語帳で「apple = りんご」と一対一で覚えても、文中での使い方は分かりません。しかし、物語などの文脈の中で何度も “apple” という単語に触れることで、その意味だけでなく、どのような場面で、どのような単語と一緒に使われるのか(コロケーション)といった情報も丸ごとインプットできます。これにより、単なる暗記ではない、生きた語彙力が身につくのです。
2. 文法を「感覚」として習得できる
私たちは日本語を話すとき、いちいち文法ルールを考えていません。これは、大量の日本語に触れる中で、脳が自然に文法のパターンを認識し、「何が自然で、何が不自然か」という感覚を身につけたからです。多読・多聴は、これと同じプロセスを英語で再現します。分厚い文法書と格闘しなくても、正しい英文のシャワーを浴び続けることで、脳が自動的に文法システムを構築していくのです。
3. 英語の処理速度が劇的に向上する
英文を日本語の語順に直して理解する「返り読み」は、リーディング速度を低下させる大きな原因です。多読・多聴では、易しい文章を速く読むことを繰り返すため、英語を英語の語順のまま理解する癖がつきます。これにより、脳内の翻訳プロセスが不要になり、ネイティブに近いスピードで英語を処理できるようになります。
成功に導く5つのやり方のポイント
多読・多聴の効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントがあります。やみくもに難しい本に挑戦して挫折しないよう、以下の5つのルールを守って実践しましょう。
- 簡単なレベルから始める(95〜98%ルール)
教材選びで最も重要なのはレベル設定です。「辞書なしで95%〜98%の内容が理解できる」、つまり1ページに知らない単語が1〜2個程度の簡単な素材を選びましょう。これが、ストレスなく学習を続けるための絶対条件です。 - 内容を楽しむことを最優先する
多読・多聴は「勉強」ではなく「娯楽」と捉えることが成功の秘訣です。ミステリー、恋愛、SF、ファンタジーなど、自分が心から面白いと思えるジャンルの本やポッドキャストを選びましょう。楽しければ、自然とインプット量は増えていきます。 - 辞書は極力使わない
分からない単語が出てきても、すぐに辞書で調べるのは我慢しましょう。前後の文脈から「たぶんこんな意味かな?」と意味を推測する訓練が、未知の単語に対する対応力を養います。物語の流れを止めずに、読み進めることを優先してください。 - 「精読」と組み合わせる
多読と並行して、少し挑戦的なレベル(理解度80%程度)の教材をじっくり読み込む「精読」も取り入れると効果的です。精読では、内容を完全に理解するために辞書を使っても構いません。学習時間の9割を多読・多聴、残りの1割を精読に充てるなど、バランスを取るのがおすすめです。 - 音声付きの教材を活用する
特に「グレーデッド・リーダーズ」などは、オーディオブックが付属しているものも多くあります。まず音声を聞き(リスニング)、次にテキストを読み(リーディング)、さらに音声を真似て発音する(シャドーイング)というように、1つの教材で複数のスキルを効率的に鍛えることが可能です。
多読・多聴は、一見すると地味で遠回りに見えるかもしれません。しかし、これこそが英語脳の土台を築き、本物の英語運用能力を身につけるための、最も確実で楽しい学習法だと言えます。まずは興味のあるジャンルの簡単な本を1冊、手に取るところから始めてみましょう。


シャドーイングのメリットとやり方

英語のリスニング力とスピーキング力を同時に、かつ飛躍的に向上させるトレーニング方法として、多くの専門家が推奨するのが「シャドーイング」です。これは、英語の音声を聞きながら、まるで影(シャドー)のように少しだけ遅れて真似して発音する練習法です。一見シンプルですが、正しく実践することで、英語脳の構築を強力に後押しする絶大な効果が期待できます。ここでは、シャドーイングがもたらす効果のメカニズムと、初心者が挫折しないためのやり方のポイントを解説します。
リスニングとスピーキングへのシャドーイングの効果
シャドーイングは単なる音読とは異なり、脳の複数の領域を同時に活性化させることで、英語の運用能力を根本から鍛え上げます。主な効果として、以下の3点が挙げられます。
1. リスニング力が向上し、ネイティブの英語が聞き取れるようになる
ネイティブの英語が聞き取れない大きな原因は、単語と単語が繋がって音が変わる「音声変化」(リンキングやリダクションなど)にあります。シャドーイングは、この音声変化のパターンを頭で理解するのではなく、自ら発音することで身体に染み込ませるトレーニングです。これにより、脳が英語の音のルールを自動的に認識できるようになり、今まで聞き取れなかった音がクリアに聞こえるようになります。
2. 発音・イントネーションがネイティブに近づく
シャドーイングの目的は、お手本となる音声の「完全なコピー」を目指すことです。個々の母音や子音の発音はもちろん、単語の強弱、文章全体のリズムや抑揚といった「英語の音楽性」まで模倣することで、自己流のカタカナ英語から脱却し、格段に通じやすい自然な発音を身につけることができます。
3. 英語を日本語に訳さず処理できるようになる
音声を聞いてから瞬時にそれを再現しようとすると、脳には英語を日本語に翻訳している時間的な余裕がありません。この練習を繰り返すことで、英語を英語のままダイレクトに処理する回路が強化されます。これが、英語脳の重要な要素である「思考の瞬発力」を鍛えることに繋がるのです。
初心者でもできる!シャドーイング実践4ステップ
シャドーイングは効果が高い反面、やり方を間違えると挫折しやすいトレーニングでもあります。以下の4つのステップに沿って、正しく実践しましょう。
- ステップ1:教材を選ぶ
教材選びが成功の9割を決めると言っても過言ではありません。「自分のレベルより少し簡単で、内容を8〜9割理解している、1〜2分程度の短い音声」を選びましょう。また、必ずスクリプト(台本)が手に入るものにしてください。最初は、学習者向けのポッドキャストや、好きな映画・ドラマの短いセリフなどがおすすめです。 - ステップ2:内容理解と音の確認(準備運動)
いきなりシャドーイングを始めるのではなく、まずは準備運動をします。最初に、音声だけを聞いて全体の内容を把握してください。次に、スクリプトを見ながら音声を再生し、文字と実際の音がどのように結びついているか、特に自分が聞き取れなかった部分の音声変化などをじっくり確認します。 - ステップ3:オーバーラッピングとシャドーイングの実践
準備ができたら、いよいよ実践です。まずはスクリプトを見ながら、音声と完全にタイミングを合わせて発音する「オーバーラッピング」を行います。これがスムーズにできるようになったら、最終段階として、スクリプトを閉じて音声の0.5秒ほど後を追いかける「シャドーイング」に挑戦します。 - ステップ4:録音して客観的に分析する
自分のシャドーイングをスマートフォンなどで録音し、お手本の音声と聞き比べてみましょう。これにより、自分の発音の癖やリズムのズレなどを客観的に把握でき、修正点が見つかりやすくなります。
自分の声を聞くのは少し恥ずかしいかもしれませんが、これこそが上達への最短ルートです。どこが違うのかを自分で発見し、修正していくプロセスが、英語力を着実に向上させます。
シャドーイングのポイント
長時間やりすぎない
シャドーイングは非常に集中力を要します。1日15分程度の練習でも、毎日続ければ大きな効果があります。
意味を考えすぎない
このトレーニングの主目的は「音の模倣」です。実践中は、意味よりも音に集中しましょう。
完璧を目指さない
最初から完璧にできる人はいません。7〜8割程度できれば上出来、という気持ちでリラックスして取り組むことが大切です。

中学生・高校生と社会人のポイント

英語脳を育てるという基本アプローチは同じですが、立場によって最適な学習法は異なります。ここでは、学生と社会人、それぞれの状況に合わせたポイントを解説します。
中学生・高校生向けの学習ポイント
学生の皆さんは、学校の授業や教材も活用できます。ただし、使い方が重要です。教材の英文を日本語に訳すのではなく、音読やシャドーイングの素材として使いましょう。付属のCDを何度も聞き、意味を理解したら、テキストを見ずに音声を追いかけて発音する練習を繰り返すことで、英語学習ツールとして役立ちます。
また、自分の好きな海外の映画、音楽、YouTubeチャンネルなどを積極的に活用するのも非常におすすめです。「楽しみながら大量のインプットに触れる」ことが、モチベーションを維持し、習得を加速させる最大の秘訣です。
忙しい社会人のための学習習慣
社会人にとって最大の課題は、まとまった学習時間の確保です。そのため、「隙間時間」をいかに活用するかが成功の鍵となります。通勤中の電車や車の中、家事をしながら、お昼休憩中など、耳が空いている時間を見つけてポッドキャストを聞く習慣をつけましょう。
また、自身の仕事や興味のある分野に関する英語の記事や本を読む「内容言語統合型学習(CLIL)」も効果的です。これは「英語を勉強する」のではなく「英語で何かを学ぶ」アプローチであり、高いモチベーションを保ちながら専門知識と英語力を同時に高めることができます。ご自身が理解しやすい範囲からでも始めれば、楽しみながら継続できるはずです。
自分に合った教材・アプリの選び方
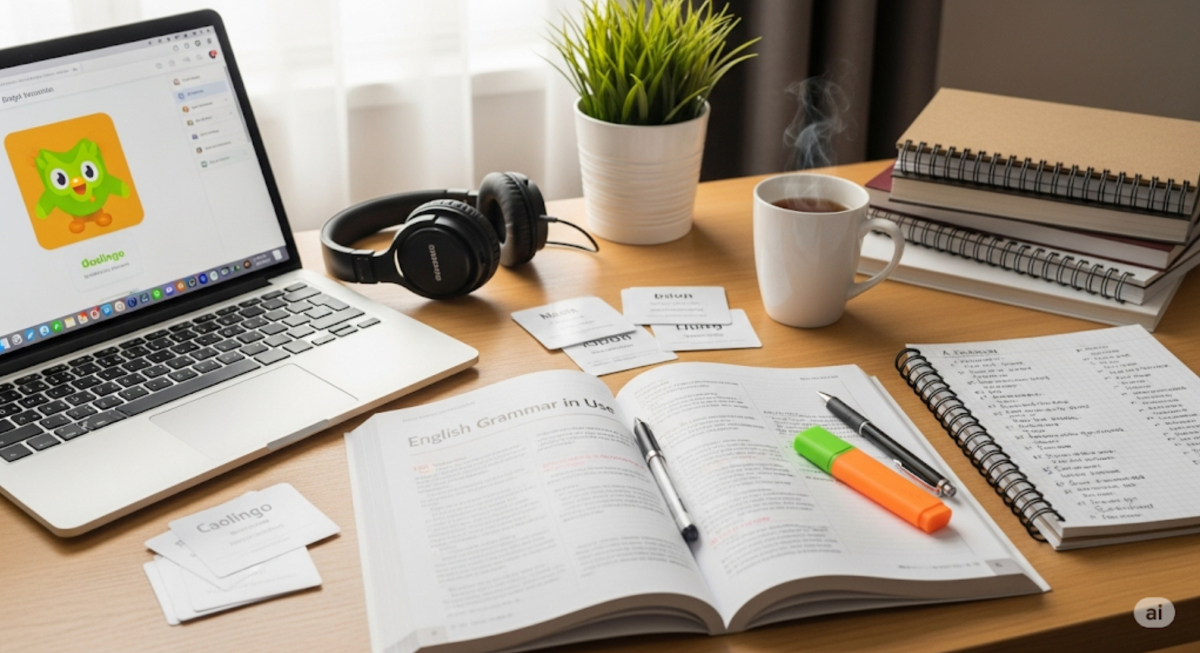
英語脳を育てるための教材やアプリを選ぶ際の重要な基準は、「①日本語の解説や翻訳が少ない(または無い)こと」と「②自分が心から楽しめる内容であること」の2点です。
以下では、レベル別にどのようなタイプの教材が適しているかをご紹介します。
| レベル(CEFR) | おすすめの教材・アプリの種類 | 選び方のポイント |
|---|---|---|
| 初級 (A1-A2) | 絵辞典、グレーデッド・リーダーズ(レベル調整された本)、子ども向けアニメ | イラストや簡単な文脈で直感的に意味が分かるものを選びます。95%以上理解できる簡単なものから始めましょう。 |
| 中級 (B1-B2) | 学習者向けポッドキャスト、YouTubeチャンネル、簡単な洋書、英語字幕付きの映画 | 自分の興味のある分野のコンテンツを選びます。スクリプト(台本)付きの教材でシャドーイングを行うのも効果的です。 |
| 上級 (C1以上) | ネイティブ向けメディア(ニュース、ポッドキャスト)、専門分野の洋書や論文など | 学習のためではなく、情報を得るため、楽しむために英語を使います。多くの英語に触れて、語彙を文脈の中で覚えるのがおすすめです。 |
以下では初心者から上級者まで無料で利用できる英語学習サイトを多く紹介しています。

英語の基礎固めのやり方について総括
記事のポイントをまとめます。
- 従来の英語の基礎固めは文法と翻訳が中心
- この方法は翻訳癖を生み会話能力の成長を妨げる
- 目指すべきは日本語を介さず英語で考える英語脳の構築
- 英語脳はリスニングやリーディングの速度を劇的に向上させる
- 英語脳は学習時の精神的な疲労を大きく軽減する
- 新しい英語の基礎固めは翻訳癖の排除から始める
- 言語は意識的な「学習」より無意識の「習得」で身につく
- 「理解可能なインプット」に大量に触れることが習得の鍵
- 特にリスニングは英語の音のルールを学ぶ上で最も重要
- 最初の1ヶ月は英語で直接考える習慣作りに集中する
- 教材やアプリは自分が楽しめるものを選ぶことが継続の秘訣
- 中学生や高校生は好きなエンタメを最高の教材にできる
- 社会人は通勤などの隙間時間を活用したインプットが効果的
- 流暢さの獲得には数千時間単位の学習が必要だと理解する
- 今日から英語を「学ぶ」のではなく「使う」意識で取り組もう